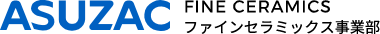表面応力の作用による転位の増殖 |セラミックス技術コラム
セラミックス技術コラム
表面応力の作用による転位の増殖

表面張力により生起される表面応力の作用による転位の増殖は焼結における塑性変形の役割を理解する上で基本的問題である。転位論により繰り返し数字的な取り扱いがなされてきた。ここではその展開を詳しく述べることはしないで、結論のみに話を限定する。
この問題は、1949年最初にConyers Herringにより「粉末冶金の物理学」という本の一章を成す「焼結の源動力としての表面張力」という論文の中で取り扱われた。Herringは小さな粒子系において、たとえ局部的な応力が存在してそれが巨視的な降伏応力を超えたとしても、表面応力を源動力としてかなりの程度の塑性流動が起こることはないだろうと結論している。
Hirthは1963年に、転位論の滑り面上における表面核生成を理論的に計算した。彼の計算は、転位論が核生成する滑り面は表面に垂直であるとする幾何学的関係に基づいている。この幾何学的関係により、Hirthは930℃における銅に対して、かなりの速度で転位の核生成が起こる臨界せん断応力はG/50(G:剛性率)あるいは約200 MPaと計算した。
EasterlingとTholenはHerringの概念を定量化し、弾性論に基づいて焼結中に転位に作用する力のコンピューターモデル計算を行った。彼らは、粒界に極めて近いところにある転位のみが粒界あるいはネック部へ移動することが可能であり、従ってネック成長に寄与すると結論している。表面応力により生起される最大せん断応力は新しい転位の核生成にはあまりに小さく、従ってネック成長は主として拡散プロセスにより支配されるに違いないとしている。
Hirthの考え方は修正されてSheehan、LenelおよびAnsellにより導入された。彼らは、転位論が生成される滑り面は表面に垂直ではなく、30°のオーダーの角度で傾いていると仮定した。この幾何学的関係に基づき、銀や銅に対してG/100(G:剛性率)あるいは約10 MPaの応力があれば、焼結温度で十分に転位が増殖されると計算した。この応力はHirthにより計算された200 MPaという値とくらべてずっと小さいが、それでも、転位の増殖は焼結の極めて初期段階においてのみ可能であるオーダーの大きさである。例えば、直径20 μmの粒子に対しては、x/a比が0.1、50 μmの粒子ではx/a比は0.06以下の場合、十分に大きな応力値になる。Schattのモデルによる500 μmの粒子に対しては表面応力による転位の増殖に必要な応力値は、ネック生成時においてのみ実現されるが、この段階では幾何学的理由から転位の増殖は起こりそうもない。
転位の増殖に対する別の機構がR.C.Morrisにより考察された。Morrisは、転位の増殖が、そのために必要とされるせん断応力が表面自由エネルギーにより供給されるには大きすぎるという考え方をしりぞけた。その代わりに、彼は球粒子と平板の間の最初の接触部は、テラスとレッジより成る円形のくさび型クラックであるというモデルを考案した。彼は、半転位論の面積と等しい面積上で対向する自由表面が消滅する際に得られるエネルギーと半転位論を形成するに要する歪エネルギーとを比較した。転位論の拡大は、球粒子と平板間の接触面積の拡大を意味し、また球表面のテラスの消滅を意味する。その結果、球粒子中心は平面方向に移動する。彼は転位の増殖のための活性化エネルギーはきわめて小さいことを見出している。焼結が進行するにつれて、転位が接触部表面で自由に核生成する。Morrisによれば、このプロセスは、テラスが小さくなって、表面自由エネルギーが転位論の歪エネルギーを供給するには不十分になったときに停止する。100 個のテラスが消滅すると、このプロセスは停止することになるが、これはネック形成のごく初期段階である。
前述の通り、Schattは、彼が観察した転位の増殖に対する理論的説明を試みている。その基本的考え方は、2重交差滑りまでの変種を含むFrank-Read機構により転位が増殖されるとするものである。Schattによれば、「表面張力応力σ=γ/ρ(γ:表面張力)はネック曲率ρに依存する。ρはρ=x2/4a(x:ネック半径、a:球粒子半径)と見積もられる」。「両端が固定された長さlsの転位片が種々の方法で湾曲して転位論をつくる(Frank-Read転位源)ためには、転位源の応力
τ0=Gb/ls
を越えなければならない。ここで、G:剛性率、b:バーガースベクトルである。
「それゆえに、焼結接触部で転位が増殖されるためにはこのプロセスの活性化および繰り返しが必要である。このことは滑り面に作用するせん断応力τpがτsを越えること、また、接触部が転位片の半円状湾曲を許容し、転位論を増殖させるような寸法であることを想定している」。
「高純度の銅単結晶板における転位源応力は(NA≈106 cm-2の場合)見積ることができる。LD≅1/√(NA )=lsという良く知られた仮定のもとに、ls ≅10-3 cm -2および1000℃(G1000 ≅104MPa、b=2.56×10 -8 cm)におけるτs≅0.26 MPaという値を得ることができる。せん断応力則(τmax=0.5σ)から、ネック部に作用するLaplas張力はσ≥2τpとなる。すなわち、接触部の転位源を活性化して転位を増殖するような状態にするにはσ>0.5 MPaという条件を満たさなければならない。Laplas張力0.5 MPaは直径0.05 cmの球粒子を用いた球粒子-平板実験に対してはx/a=0.2であることに対応している。これは、x/a=0.15~0.20の範囲で転位ロセットの成長が停止するという実験結果と良く一致する。
ネックにおいて転位の生成を可能にする近似的な引張り応力値0.5 MPaという値はHirthによって計算された200 MPaという値よりずっと小さいし、Sheehan、LenelおよびAmsellの値10 MPaよりも小さい。このネックにおける限界引張り応力は、転位密度を106 cm-2とし、この転位密度から計算した転位間平均距離とFrank-Read源の長さを用いている。Schattのこの仮定が合理的なものか否かがここでは問題である。
Schatt自身は彼の論文の最後に次のように書いている。「静的な意味における転位片のピン止めに言及するだけで良いのかどうか、あるいは動的な高温増殖過程には注意を向けるべきではないのではないかという議論については疑問を差しはさまざるを得ない。そのような転位源が必要ではないということも考えられる。接触部の粒界の質、少なくともその通常の高角度粒界への変化過程における、あるいはそれが影響を受ける応力場と隣接する格子体積との相互作用の可能性のみが、接触領域における転位の形成(放出)の理由であり、“源”であるとも考えられよう」。
焼結中に表面応力の作用により転位が核形成されるのか、またどのように形成されるのかという問題は広く開かれている。この疑問に対する解答が、焼結における塑性流動の役割を決めるために必要とされている。
焼結-ケーススタディ 宗宮 重行・守吉 祐介 共編
お問い合わせ
特注サイズや形状も、1点から承ります。
お気軽にお問い合わせください。
-
アスザック株式会社
ファインセラミックス事業部受付時間:9:00~17:00(土日祝休み)
FAX : 026-251-2160